ピアノを学習する上で
4期【バロック、古典、ロマン、近現代】の曲を
バランスよく取り入れることは
とても大切です。

そのためには、意識して
テキストを選択しなければ
偏ってしまいがちです。
よく〝食べず嫌い〟ということを言いますが
ピアノの学習に於いても
弾いたことのない時代の曲は
好き嫌いの前に
興味を持つこともできません。
せっかくピアノを習うのなら
色々な時代の曲に触れ
それぞれの時代の演奏スタイルを
経験して欲しいと思っています。

ここで4期の、それぞれの特徴ついて
簡単にご説明しておきます。
◾️バロック期◾️

多声部音楽の時代。
メロディーと伴奏ではなく
いくつものメロディーで、曲が構成されている。
音楽家:バッハ、ヘンデルなど
◾️古典期◾️

メロディーと、和音が元になった伴奏。
客観的で形式重視。
音楽家:モーツァルト、ベートーヴェンなど。
◾️ロマン期◾️

感情や情景を自由に表現。
個性、独創性、各国の民族性が強調される。
音楽家:ショパン、リスト、シューベルトなど。
◾️近現代◾️
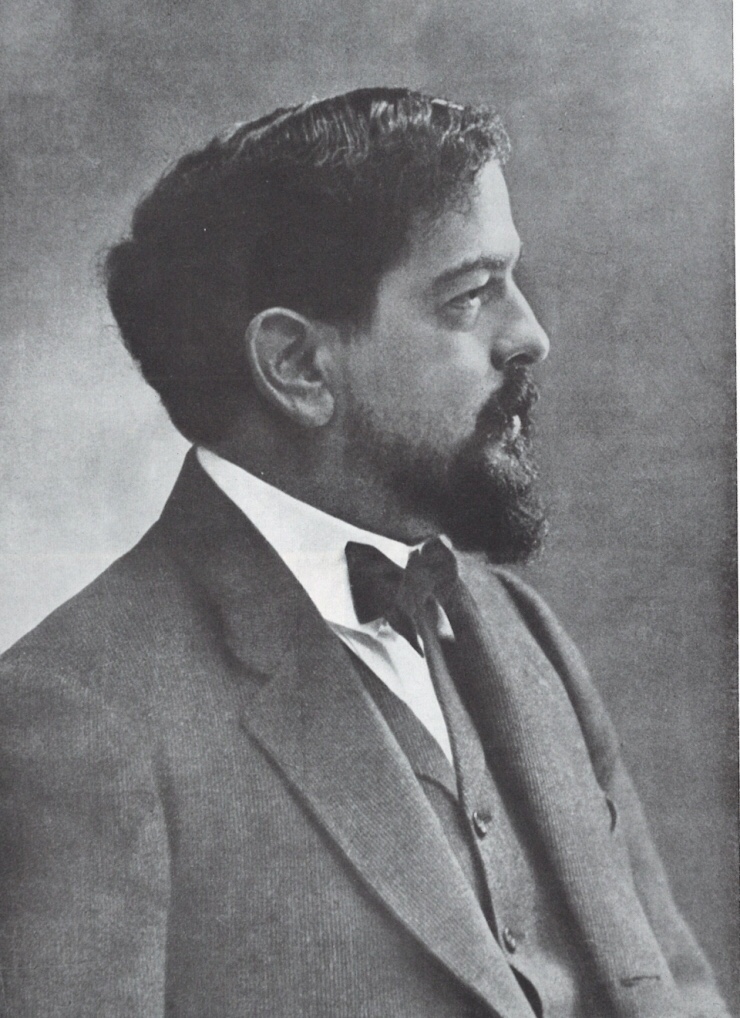
印象主義の音楽、長調・短調のない音楽
12音技法、内部奏法、電子音楽など
さまざまな無制約な表現。
音楽家:ドビュッシー、サティなど。

ざっと並べただけでも、その特徴は全く異なり
4期、それぞれの学習をすることの大切さが
お分かり頂けると思います。

特に、初級のテキストには
古典期に偏ったものが、多いように感じますが
できるだけ早い時期に
バロック期に、触れさせたいと考えています。
バロック期の音楽は
左手で、メロディーを歌うことを、経験できます。
左右の手で、対話しながら作り上げていく音楽は
心を豊かにしてくれます。

ロマン期の音楽は、その自由さや
心の奥深く響く、美しいメロディーやハーモニーなどから
ピアノの音色の美しさに
改めて気づくことができる、と確信しています。

近現代の曲は、特に初級では
意識しなければ、経験する機会が少なくなります。
しかし、何の先入観もないこの時期にこそ
是非触れて欲しいものです。

様々な時代の音楽を学ぶことで
興味を失うことなく
ピアノの持つ、奥深い魅力に気付いて欲しい
そう考えています。


