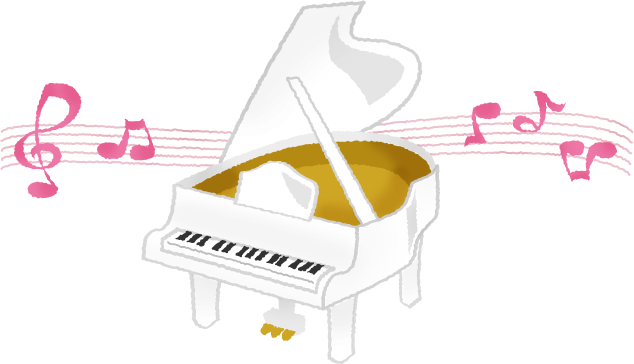楽典とは、音楽の活動のための
必要最低限の知識のことで
〝音楽の文法〟とも呼ばれています。
文法を知らなくても、言葉を話せるように
楽典を知らなくても、楽器を演奏することは
可能です。
ですが、楽典の知識が
より知的な演奏に、結びつきます。
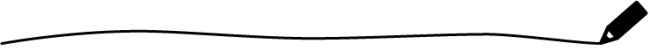
楽典の内容は幅広く、音楽用語に始まり
リズムの仕組みや、調性など
曲を理解するために、必要なことばかりです。
音楽用語や音楽記号については
レッスン中に、できるだけ説明していますが
いろんな仕組みを、系統だてて学ぶには
やはり、テキストが必要です。
当教室では、希望者には楽典の問題集を与えて
宿題にしています。
1ページの分量はわずかで
負担は大きくはありませんが
継続するのは、難しいようです。
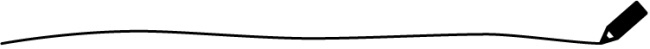
楽典歴数年のRちゃん(小6)。

今日のレッスンで、和音を弾いた後
「どうして端の音程は7度なのに
きれいな響きがするんですか?」
と、疑問を投げかけてきました。
演奏のかたわら、度数まで考えているとは!
(しかも初見の最中に)
私の回答は
「端の音程は7度でも、この和音は
3度の積み上げで、できているから・・・」
急に振られて驚きながら
何とか答えを出しました。

実際には、和音の響きは
音の組み合わせや、和音進行により
決まるので、どの音程が濁るとは
単純には言えません。
今回は、以前学習した音程を
練習曲の中で疑問に感じ
解決することができました。
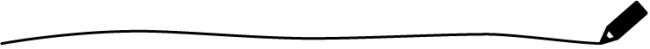
Rちゃんは、その他にも折に触れ
楽典で得た知識をもとに
色々な質問をしたり、自分の考えを述べたり
ただ演奏するだけではなく
論理的に理解しようとしています。
深く考えることのできるRちゃんが
これから中学生になり
どのように成長していくのか
とても楽しみです。